やってはいけない悪徳商法!
うまい話には裏がある!
悪徳商法に遭わないように! |
うまい話には裏がある!
悪徳商法に遭わないように! |
もし悪質な業者の被害に遭ってしまったら、絶対泣き寝入りしないで、クーリングオフできるものは遠慮なく実施すべきです。クーリングオフまたは中途解約できるかどうかや、その他解らないこと、相談事があれば次のところで相談に乗ってくれます。 (財)日本訪問販売協会 国民生活センター |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的に契約当事者の合意によって一度成立した契約は一方的に解消できないのが法律上の原則です。 契約に基いて製品を製造したり、送付したり、引き渡したりする等、いろいろなことが契約から生じて、その契約が一方的に解消されてしまうと、予想しない損害が相手方に生じるばかりか、契約そのものの信頼性が失われるためである。 仮に契約を解消した場合は、それから生じた損害を相手側に払わなければならなくなりますが、 セールスマンによる訪問販売などで甘い勧誘にのせられ、つい不要なものの購入契約をしてしまう人もいます。 そうした人を保護するため、消費者を保護する観点から、例外として、一定の期間(冷静になってもう一度考え直す、又は人に相談する)内には違約金なしに(無条件で)契約解除(契約申込みの撤回。つまり契約を無かった事にすること)ができるとした制度がクーリングオフです。 その期間は、以下のように取引(契約)の内容によって異なります。
クーリングオフで契約を解除したときは ?支払った現金は、全額返金される。 ?商品を受け取っていた場合は、販売業者の負担で商品を引き取らせることができる。 ?工事などによって、土地や建物が元の状態と変わってしまったら、無料で元の状態に戻すよう販売業者に 請求することができる。 ?損害賠償や違約金を支払う必要はない。(これらはあくまでの法律上の効果で、実際にこのことが実行される とは限らない。業者が逃げたり、倒産した場合にはその実行は不可能となることが多い) ?契約したのが営業所、店舗以外の場所であること(路上などで呼び止められて営業所、店舗に連れて行かれ た場合や、目的を告げられずに電話などに呼び出された場合も、クーリングオフの対象となる)が必要である。 クーリングオフできない場合 ?商品と引き換えに3,000円未満の代金の全額を支払った場合。 しかし、支払方法が現金一括払いでなければ、3,000円未満でもクーリング・オフの対象になる。 ?健康食品、不織物、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、家庭用医療用洗浄器、防虫剤、殺虫剤、 防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤、化粧品、毛髪用剤、石けん(医薬品を除く)、浴用剤、 合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙化粧品など、使うと商品価値が 無くなる商品を使用した場合。(セット商品は開封した商品のみ) ?自動車の購入契約 ?事業用や営業用に購入したもの ?日本国外へ販売したもの ?国や自治体や公共団体が販売したもの ?通信販売 ?自分から店や営業所に行って買った場合。(ホテルなどでの展示会での場合は店舗と見なされクーリングオ フできないが、展示会の開催期間が1日〜2日など短期の場合店舗と見なされずクーリングオフできる場合が ある) 以上の場合クーリングオフできない。 なお、クーリングオフしないと書面で誓約させたり、名刺の裏にキャンセルしないと書かされ、署名・押印させたり、なつ印させられたり、商品の袋を開けたから、梱包用の袋を捨てたから、クーリングオフできないといいう悪徳業者がいるが、もちろんクーリングオフができる。 クーリングオフの方法 ?上記の期間内に行なわなければならない。郵便局の消印が契約した日から期間内であれば有効である。 この期間を経過すると、契約解除は難しくなり、たとえ業者が契約に応じても、違約金を取られる場合がある。 ただし、契約書にクーリングオフのことが書かれていなかったら、期間を過ぎていてもクーリングオフができる。 ?クーリングオフは電話ではなく、書面で通知し、書面を発した時にその効力を生じる。 ?書面での通知は内容証明郵便(これがもっとも確実)か、ハガキ の場合は簡易書留か配達証明付郵便にす る。 ハガキで出す場合、裏と表のコピーを必ず取っておきます。  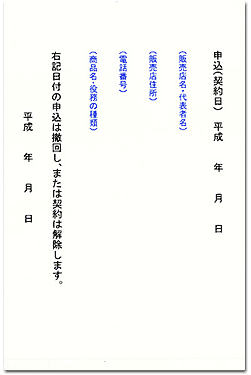
書面・サンプル 内容証明郵便 郵便物の特殊取扱の一で、郵便物の内容(文書・日付・差出人・あて先)を謄本で証明するものである。 内容を後日の証拠として残しておく必要のあるとき(法律行為としての通告など)に利用される。(郵便局がその謄本の1通を保管、証明する)すなわち、差出人は同じ文書を3通作成、それを郵便局に提出して手続きを受け(郵便局で、同一内容であると認めたときは、通信日付印や内容証明郵便である旨のスタンプなどが押される)、1通を差出人が、1通を郵便局が保管し、他の1通が相手方に配達される仕組みである。 配達されたことが証明される、配達証明を併用することが多い。 簡易書留 郵便物の引き受けと配達だけを記録し、送達の途中の記録を省略する書留郵便で、紛失や毀損(きそん)の場合は、郵政省が一定の限度内で差出人に賠償を行う。 配達証明付郵便 郵便物の特殊取扱の一で、郵便物を受取人に配達・交付した事実を、差出人に証明する扱い。 ?代金の支払いをクレジット契約とした場合は、購入契約を結んだ業者とクレジット契約を結んだ信販会社の 両方に送付する。 ?ハガキをコピーし、配達記録の受領書といっしょに保管する。 ?商品を受け取っておらず、また代金も支払っていない場合と、商品を受け取り、代金の一部を支払っている 場合とでは、書面の書き方に若干の違いがある。 |
 152-0035 152-0035東京都目黒区自由が丘二丁目十六番十二号 RJ3 春宮 正勝 TEL : 050-5343-7214 E-mail : info@harumiya.net |